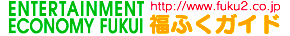

〒910-2153 福井県福井市東郷二ヶ町6−1
東郷公民館 TEL 0776−41−0306
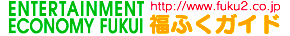
 |
| 福井市 越前東郷の紹介 |
|---|
|
〒910-2153 福井県福井市東郷二ヶ町6−1 |
|
東郷公民館 TEL 0776−41−0306 |
| 堂田川のせせらぎを中心に豊かなふるさとの風情が漂う街。 |
|
|
東郷の町並みを流れる堂田川(徳光下江用水路)は、足羽川の清流を取り入れ、古い荘園の時代から、農地や生活用水に利用されていました。両側の街道は、江戸時代、大野藩主の参勤交代時に北陸街道への近道となり、人馬が盛んに往来して宿場町として賑わったようです。現在では水と親しむ楽しい親水路が完成し、清らかな水の流れとそこに生きる魚たち、それぞれ異なった表情を持つ14の橋により、安らぎのある豊かな「ふるさと」の風情を漂わせています。 |
|
|
|
◆ 堂田川(どうでんがわ) |
|
|
JR越美北線の越前東郷駅から徒歩3分、東郷の町の中心道路に流れる親水路、堂田川の川沿いには、色鮮やかな美しい花々が植えられていて、通りを利用する人々に、やすらぎと憩いの雰囲気を与えています。川の流れの中にはたくさんの錦鯉も見られます。 |
|
|
|
|
|
◆ 東郷町の歴史 |
|
|
東郷の名は、朝倉期の荘園、「東郷荘」として初めて現れ、貞治5年(1366年)、朝倉高景にこの地の地頭職が与えられます。朝倉氏は一乗谷に拠を構え、槇山には一乗谷の出城が築かれました。朝倉氏滅亡後、天正13年(1585年)、長谷川秀一が東郷に入部し、城下町としての整備がこの時代に進んだと考えられます。槇山に築かれた東郷城は、秀一の死後入城した丹場長昌が関が原の戦いにおいて西軍に属したため廃城となり、江戸時代に入ると、東郷は宿場町としての賑わいを見せるようになりました。現在も東郷には、長谷川秀一や朝倉氏縁の神社、仏閣などが多く残り、福井の歴史を知る上で重要な地となっています。 |
|
|
|
|
|
◆ 花山権現 毎年5月5日 |
|
|
東郷の栃泉町の男の子たちで行われる民俗行事。5月5日の端午の節句に、子供たちがハチマキ姿で手に花山を持ち、「花山権現」と連呼しながら町を一巡りする。“花山”とは、子どもの身長ほどの竹の先にツツジ・藤の花・牡丹など季節の花を円筒状に飾りつけたもので、“三役”だけは花山のほかに竹・杖を持って花笠をかぶる。 |
|
|
|
|
|
◆ 東郷の川床イベント |
|
|
2017年10月25日、米どころ「福井市東郷地区」にある3つの酒蔵のお酒が一堂に会した日本酒Barが、堂田川の川床で一夜限定オープンしました。会場横の照恩寺では、県内外からも新しい法要スタイルとして注目されているテクノ法要が開催され、ニコニコ生放送では川床Barとテクノ法要の様子が全国に生中継されました。東郷のお酒と堂田川の秋夜、また楽しみたいです。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東郷の川床イベント |
東郷の川床イベント |
東郷の川床イベント |
|
|
|
||||

|